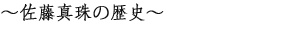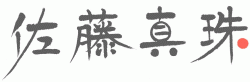愛媛県の西北に位置する明浜町で佐藤真珠は養殖をしています。明浜町は全国でも有数の美しいリアス式海岸、石灰質を含む段々畑のみかん山を背に、波穏やかな海が広がります。
 鎌倉時代から存在する段々畑では地元の生産者団体が農薬の使用を極力抑えたみかん栽培を行っています。山から流れ出る豊かな水は真珠の形成に必要なカルシウムを多く含み、豊かな海を作ります。佐藤真珠では単に生産活動をするのではなく、この豊かな海を守りながら、次世代に引き継げる漁業を目指し日々の養殖作業を行っています。
鎌倉時代から存在する段々畑では地元の生産者団体が農薬の使用を極力抑えたみかん栽培を行っています。山から流れ出る豊かな水は真珠の形成に必要なカルシウムを多く含み、豊かな海を作ります。佐藤真珠では単に生産活動をするのではなく、この豊かな海を守りながら、次世代に引き継げる漁業を目指し日々の養殖作業を行っています。
苦難のスタート

昭和42年、それまで家業としていたイワシ漁から真珠養殖に転換しました。真珠養殖を始めて間もなく初代の佐藤文雄が病で倒れ、その妻喜美子と高校を卒業したばかりの長男宏二の2人で仕事をやりくりしました。真珠は養殖して出来上がるまでに1年以上かかります。その間の収入はゼロ。親戚中を回り運転資金を工面するなど苦難の日々が続きました。ようやく事業が起動に乗り始めた3年目、今度は全国的な生産過剰による価格の暴落が起こり、漁協の指導の下、生産調整が行われました。1年間苦労して手塩にかけて育て、出来上がった真珠を焼却炉に入れて処分しました。その当時の悔しさ、無念の気持ちは今でも忘れることができません。
頑張れば報われる時代

昭和50年に入り、高度経済成長と共に真珠産業も好景気になりました。頑張ればその分だけ報われた時代でした。早朝5時より沖に出て、夕方は真っ暗になるまで一生懸命働きました。その甲斐あって、現在の使用している船、作業場など、真珠養殖に欠かせない設備を充実させることができました。しかし、このような時代も長くは続きませんでした。
アコヤ貝の大量へい死
平成9年頃、長崎県で原因不明のアコヤ貝大量へい死が発生しました。その後、九州全県に広がり、ほどなくして愛媛県でも大量へい死が発生しました。当時、佐藤真珠では25万個のアコヤ貝を養殖していましたが、残ったのは5万個ほどという時期もありました。作業する度に死んでいくアコヤ貝を目の当たりにし、どうしたらいいのかわからず悔しい日々の連続でした。そんな中、大量へい死の原因として、過密養殖、ウイルスによる感染症説、魚類養殖で使用するホルマリンの薬害説などの様々な要因が考えられるようになりました。それらの要因の中でも、真珠生産者はホルマリンの使用に着目し、皆で団結しホルマリン不使用の活動を始めました。地元湾内でのホルマリン数値の検出を始めとした継続的な漁場調査、県政や水産庁などへの働きかけなどその活動は多岐にわたり、地元新聞紙などでも取り上げられました。同じ漁業関係者との話し合いということもあり、数年に渡り紆余曲折を経て、ようやく成果が表れ、平成16年には、全国初の環境保全に関する町条例発布、愛媛県議会でも条例化が採択され、ホルマリンの使用は原則禁止されました。
そして、平成17年以降、アコヤ貝の異常なへい死は無くなりました。
自然と共に~環境を守りながら継続的な養殖へ

真珠の品質の良し悪しは海の環境に大きく左右されます。この美しい海を守るため地元漁協などと協力しながら、合成洗剤の不使用、廃油からの石鹸作りを行っています。また、平成21年度より本格的にワカメの栽培も始めました。ワカメは海中のリンや窒素を吸収し酸素を作ります。緑豊かな海を目指し活動しています。
私たちは自然に生かされ、自然の恩恵を受けることで漁業に携わることができます。この自然を守り続けること、次世代に引き継げる美しい海をつくることが私たち生産者の使命だと考えています。
 鎌倉時代から存在する段々畑では地元の生産者団体が農薬の使用を極力抑えたみかん栽培を行っています。山から流れ出る豊かな水は真珠の形成に必要なカルシウムを多く含み、豊かな海を作ります。佐藤真珠では単に生産活動をするのではなく、この豊かな海を守りながら、次世代に引き継げる漁業を目指し日々の養殖作業を行っています。
鎌倉時代から存在する段々畑では地元の生産者団体が農薬の使用を極力抑えたみかん栽培を行っています。山から流れ出る豊かな水は真珠の形成に必要なカルシウムを多く含み、豊かな海を作ります。佐藤真珠では単に生産活動をするのではなく、この豊かな海を守りながら、次世代に引き継げる漁業を目指し日々の養殖作業を行っています。